「今よりも一歩幸せに!」 どうも〜 “釣りって、学べる。”です。
今回は、これからハイシーズンに入る「アマダイ」の釣り方について解説していきたいと思います。
このあと順を追って説明していきますが、アマダイは釣り方のゲーム性が高くて、食べてもひじょーーに美味しい、家族にもめちゃくちゃ喜ばれる魚です。
釣りに行くと言った時の家族の視線・・厳しいですよね?
これを視聴してくれている世のお父さん!これを釣って帰れば、家族に冷たい目で見られなくて済みますよ!
ということで、本日の目次です。
1 アマダイとは?
2 アマダイ釣りのタックル
3 アマダイの釣り方
の順に解説していきます。
動画の最後には、特典パートとしてアマダイのおすすめレシピをお伝えしますので最後までご覧いただけたら幸いです。
それでは、本編に入ります。
【1 アマダイとは?】
アマダイは、アカアマダイスズキ目アマダイ科アマダイ属に属する魚です。
日本に生息するアマダイ属の魚は、5種類と言われています。
このうち、ハナアマダイとスミツキアマダイは分布域が沖縄や男女群島近海と非常に限られているので、私たちがお目にかかる可能性があるのは、アカアマダイ、シロアマダイ、キアマダイの3種類です。
つまり、単にアマダイという魚がいるわけではなく、最も一般的なアカアマダイのことを指します。
アマダイの仲間は、いずれも砂泥地を好み、器用に穴をほって暮らしています。
主食は、ゴカイ類や甲殻類などで、後ほど改めて説明しますが、釣りエサも、オキアミを使用します。
アマダイは種類によって生息する水深が違って
シロアマダイで30〜100メートル
アカアマダイで50〜150メートル
キアマダイは100〜300メートル
となっています。
そして、1番大きくなるのが、100〜150尾に1尾釣れるか釣れないかと言われている、幻のシロアマダイです。
60センチを超える個体もあるというから、相当な迫力ですね。
まあ、シロと言っても、グレーがかった薄いピンクであまり綺麗な色ではないのですが、実際はkg15,000〜30,000円はくだらない、超ーー高級魚なので見た目で判断してはいけません!
家族を説得してでも行きたくなってしまいますよね?
【2 アマダイ釣りのタックル】
それでは、タックルについて説明していきます。
かつて、アマダイ釣りに使用するオモリは80号が標準とされてきました。
しかし、圧倒的な強度を誇るPEラインの登場で、オモリ40〜60号とPE2号以下の「ライトスタイル」が主流になっています。
タックルが軽くなる分疲労も少なくて、繊細なアタリも捉えることができるようになり、かけた後のやり取りも含めて、グッと楽しくなりました。
ですから、竿は、40〜60号の使用オモリに見合った全長2メートル前後のものを使用します。
調子は7:3〜8:2が使いやすいです。
現在は、ライトアマダイ専用竿も発売されていますが、とりあえずこの条件を満たしていれば、一般的なゲームロッドで問題ありません。
次にリールについて解説します。
アマダイ釣りでは、小型のベイトリールが主流となっています。
カワハギ釣りなどで使っているものを流用しても大丈夫ですが、先ほど説明したように、水深が深いので、小型の電動リールをおすすめします。
回収するだけで、腕が疲れて「もう無理〜」なんてことになりかねませんからね。
アマダイ釣りでは、キャストのメリットがほぼありませんが、もちろんスピニングリールを使うことも大丈夫です。
ラインは、PE0.8号〜2号を使用します。
ライトの意味がなくなってしまうので、くれぐれも2号より太いラインを巻かないように注意してください。
ここでまた、特筆すべき点があるのですが、このタックルはテンヤタチウオ、関西や九州方面ではあまり馴染みがないかもしれませんが、コマセマダイに流用することができます。
タチウオ釣りやマダイ釣りについては、「タチウオの極意」「マダイの極意」として以前詳しい動画を上げていますので、ぜひそちらも、ぜひご覧ください。
つまりこのタックルを揃えることができれば一年中、釣りものに困らなくなるのです。
最高だと思いませんか?
アマダイの仕掛けは、全長2メートル、ハリス2〜3号の片テンビン2本バリが基本です。
市販のものを使用して問題ありません。
市販の仕掛けの多くは、枝スの接続に親子サルカンなどを使用しています。
サルカンを使用することで、ヨレや絡みを防ぐほか、パーツを分解できるので、傷んだ部分だけを交換できるメリットがあります。
アマダイ用のハリは、チヌ3〜4号、丸カイズ12〜13号などが好まれますが、市販のものはセットになっていますので、そのまま使用して問題ありません。
そして、アマダイ釣りではテンビンを使用します。
ライトアマダイ用のライトテンビンも存在しますが、一般的なテンビンで問題ありません。
これは船宿が、根掛かりして紛失した場合のみ買取という形で無料で貸し出してくれることが多いので、改めて購入する必要はありませんが、必ず船宿に確認してください。
オモリについては、40〜60号をPEラインの号数によって使い分けますが、その日の混雑具合や潮の速さに大きく影響されるので、必ず船長に確認するか、もしくは船宿を予約する際に確認するのが確実です。
でないと、隣の人とすぐにおまつりして釣りどころではなくなってしまいますので注意してください。
ちなみに、タングステン製のオモリもありますが、40号で4,000円もするので、ロストした際は・・・わかりますよね?
持ち物としては、クーラーボックス20リットル、竿掛け(貸し出し有り)、メゴチバサミ、ハリ外し、ハサミ(絶対)、プライヤー、ナイフ、タオルなどがあればできますので、大きなタックルボックスも必要ありません。
【3 アマダイの釣り方】
タックルも分かったところで、アマダイの釣り方について解説していきます。
まず、エサは、先ほども少し触れましたが、オキアミを使います。
コマセを使用しないので、自身も車も汚れないし、臭くなりません。
コマセの後処理で、家族から疎まれているお父さん、たくさんいますよね?
これなら嫌われなくてすみますよ。
話を戻します。基本的に、冬場の釣りなので、出しっぱなしでも問題ありませんが、天候によってはクーラーボックスに入れたりした方がいいです。
オキアミについては、代金に含まれていることが一般的ですが、もちろん釣具店などで買って自分で用意してもいいです。
ランカーを狙っているとかでなければ、船宿のオキアミで全く問題ありません。
そして、エサの付け方ですが、少しだけ加工が必要です。
オキアミの尻尾をハサミで切ったあと、そこからハリを刺してチモトまでエサで覆い、ハリ先をオキアミノのお腹側から出して完成です。
ここで、ハサミが必ず必要になるので、忘れないように注意してください。
それでは、実釣方法を解説していきます。
船長から、釣り開始の合図があったら、仕掛けを船べりから垂らし、利き手で竿、もう片方の手でオモリを持ち、振り子の要領で軽く前方に投入します。
慣れないうちは、仕掛けを投入してから、オモリを落とした方がやりやすいです。
オモリが底に着いたら、糸ふけを素早く巻き取り、仕掛けが落ち着くまで10秒ほど待ちます。
ここから、アマダイ釣りの面白いところです。
海底の感触を確かめるように、オモリで海底を数回小突きます。
この時発生する、音、振動、煙幕でアマダイにアピールするのです。
そして、竿先を海面まで下げて、糸ふけを取った状態から1メートル巻き上げ、ここを基点とします。
全長2メートルの仕掛けなら、ここで枝ハリが海底から浮き上がっているイメージです。
そして、ここですぐにココンという繊細なアタリが出ることが多いので、気を抜けないと同時に最も興奮する場面です。
ここで当たりが出なかった場合、仕掛けを再度落とし込むのではなく、聞き上げるように1メートル上げます。
今度は、先バリが海底から離れるイメージです。
ここでもアタリがなければ、エサがゆらゆらと落下する様子をイメージしながら、ゆっくりと1メートル下ろします。
ここでも当たりがなければ、ゆっくり1メートル聞き上げます。
基本的にこの動作の繰り返しです。
ポイントは、比較的平坦な砂泥地とはいえ、傾斜のある場所、カケアガリを好む傾向があるので、誘いを何度か繰り返したら、底ダチを取り直し、最初の小突きから再スタートさせます。
そして、誘いが少なすぎても多すぎてもヒット率が低くなるのが、この釣りの奥深いところ。
その時々の正解の誘い方を見つけていくことが、釣果UPに繋がります。
この釣りでは、5分に1回は仕掛けを取り込み、オキアミをどんどん交換した方が良い釣果に繋がります。
アマダイのアワセ方は、先ほど繊細なアタリがあると説明しましたが、少しでも違和感を感じたら、基本的に即アワセしてください。
それがダメなら、一呼吸おくパターンで試してみてください。
アマダイは大型にもなると、マダイの三段引きにも似た強烈な突っ込みをみせます。
大型ほどバレやすいので、最初の20メートルほどは手で巻いて、その後電動で巻き取った方が無難です。
ここで、頭の片隅に入れておいて欲しい釣法があります。
それは、置き竿釣法です。
基本的にアマダイ釣りは「釣れる釣り」ですが、妙にアタリが遠い日があるのも事実で、普通、渋ければ渋いほど誘いに力を入れるのが釣り人の性というもの。
しかし、アマダイ釣りの場合は、頑張れば頑張るほど逆効果となるケースが多いです。
なので、初心者が竿頭になったりするケースがあるのも、この釣りの面白いところと言えます。
【まとめ】
それではまとめです。
アマダイは、シロアマダイという幻の超高級魚が釣れる可能性もある夢のある魚です。
タックルは、テンヤタチウオ釣りに流用できたり、汎用性にも優れています。
エサにはオキアミを使用するので、車や洋服が汚れて、えも言われぬ臭いのせいで家族から嫌われる心配もありません。
そして、この後の特典パートでも紹介しますが、非常に美味しい魚でもあります。
これほど完璧な釣りってあります?
この動画がきっかけで、アマダイ釣りに挑戦していただける方が出てくれたら嬉しいです。
【特典パート】
それでは特典パートに入ります。
ここでは、アマダイのおすすめの食べ方を2つ紹介したいと思います。
まず1つ目は、アマダイの最も有名な食べ方と言っても過言ではない「松笠揚げ」です。
これは、魚のウロコを付けたまま、高温の油で揚げた料理です。
ウロコが立つことで松ぼっくりのような見た目に似ているため、こう呼ばれています。
その食感は、見たとおりサクサクでかつ身はふんわりとしており、アマダイでしかできない調理方法なので、一度食べてみることをオススメします。
そして2つ目は、昆布締めです。
アマダイは、非常に美味しい魚ではありますが、「水っぽさ」がある魚でもあります。
そこで、昆布締めにして熟成させることで、適度に水分を抜きつつ、旨みが最大限に引き出されます。
昆布締めされた刺身は、艶があり、程よく引き締まった身は甘みも強く、こちらもぜひ一度食べて欲しい食べ方です。
他にもオススメの食べ方があるよという方は、ぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。
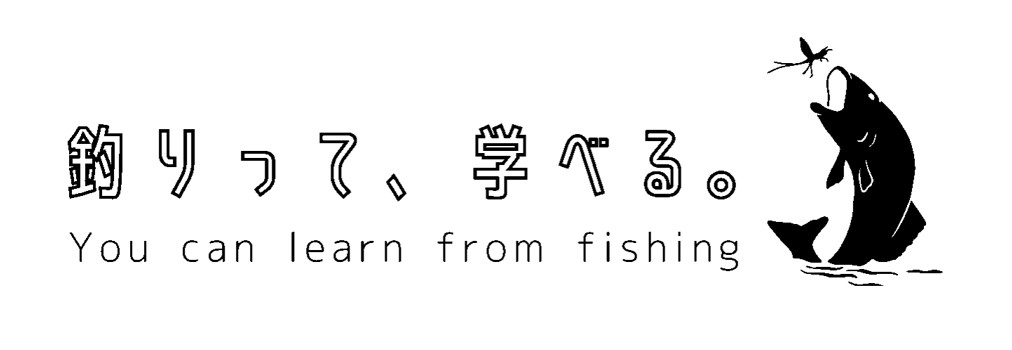



コメント